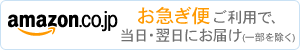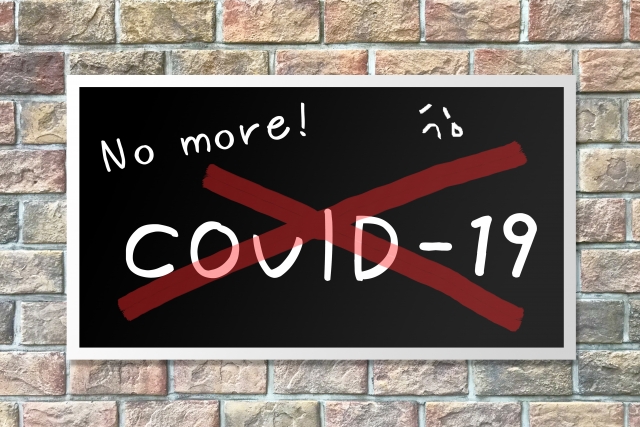小規模企業共済のメリットとデメリット 節税効果はあるがリスクも
- 2023/2/9
- トピックス
以前の記事でも紹介しました「小規模企業共済」。
合わせて読む 経営者のための退職金や事業資金の貸付まで 小規模企業共済とは
小規模事業を営む個人事業主の方や会社役員の方の退職金代わりになったり、事業資金の貸付制度があったりと、何かと役に立ちそうな制度ですが
世の中、上手い話ばかりではありません。
そこで今回は小規模企業共済のメリットとデメリットについて整理したいと思います。
掛金が全額控除 経営難の時は事業資金の借入もあり
まず小規模企業共済の最大のメリットは
掛金が全額、所得控除の対象になることです。
確定申告の際に課税対象所得から控除できるので、非常に高い節税効果が見込めます。
課税所得が200万円だったとしても、掛金が月額7万円であれば年間で129,400円もの節税になります。
課税所得が1000万円であれば、同じく掛金月額7万円で367,000円の節税となります。
この月額掛金は1000円から7万円まで500円単位で自由に設定ができます。
しかも、加入してからも自由に増減できますので、その時々の経営状況によって調整ができます。
さらにん経営が悪化して掛け金の支払いが難しい場合には、一時的に支払いを止める「掛け止め」も可能です。
この共済金は退職時や廃業時に受け取ることができるのですが
「一括」「分割」「一括と分割の併用」
から選ぶことができます。
一括受取は「退職所得」、分割受取は「雑所得」扱いとなりますので、事業所得と比べると、税負担が大幅に減ります。
この小規模企業共済は
退職金代わりに使うだけでなく、事業資金の貸付制度があります。
加入者は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を低金利で利用することができます。
即日貸付けも可能で迅速に事業資金を借入できる非常に便利な制度となっています。
借入は掛け金の範囲内で10万円〜2,000万円以内でできます。
短期の掛金納付はデメリットになる 20年未満では元本割れも
では次にデメリットです。
まずは掛け捨てリスクです。
掛金納付月数が6ヶ月未満の場合は共済金は一部しか受け取ることができません。
また12ヶ月未満の場合でも
準共済金(法人の解散、病気や怪我、65歳未満での役員退任)
解約手当金を受け取ることができません。
匡、災害などやむを得ない場合は、この例には当てはまりません。
また、12ヶ月以上の納付月数があっても、20年未満の解約では全額ではなく、元本割れをしてしまいますので注意が必要です。
次のデメリットが受け取り時の課税です。
掛金自体は全額が控除対象をたり節税になりますが、受け取った際には退職所得や雑所得として課税対象となります。
匡、退職所得は特別な軽減が図られますので、税負担は幾分かは軽減されます。
以上が小規模企業共済のメリットとデメリットです。
これらを踏まえて、加入するかどうかじっくりと検討してみてください。